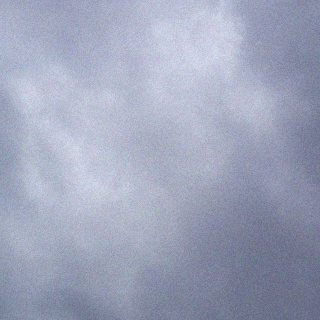今月の日経の私の履歴書は元日立製作所社長の川村隆さんであるが、先日とても考えさせられる文章があった。
少し長いが以下に引用する。
当時のように会社の体力が落ちて来ている時には、本来は状況を分析し、戦略を立て、議論を深め、社内外に説明をし、その上で改革を断固実行すべきなのだ。それなのに日々の膨大な仕事量に流されることを良しとしてしまった。自覚は無かったが、一種の逃避をしながら、懸命に働いている形を作っていた、と言われても仕方がない。忙しく髪を振り乱して働いている人間が本来の仕事をしているとは限らないことが分かった4年間だった。
これ程の人でも「一種の逃避をしながら、懸命に働いている形を作っていた」という事をしてしまうのかと少し驚いた。スタークスは小さい会社であり、経営者であっても自ら設計書の作成をしなければならない事も多い。設計書の作成をしていれば仕事をしている様には見えるし、慣れた業務をするのは楽である。しかし、それが本来の仕事なのかは自分自身でよく考える必要がある。会社の成長を求めるのであれば、経営者が最も時間を費やすべき仕事は「機会の追求」であり「現状の維持」ではないはずだ。
以前読んだ本にこんなことが書かれていた。
「ダメな会社は社長が部長の仕事をし、部長が課長の仕事をし、課長が平社員の仕事をし、平社員は会社の将来を嘆いている。」
本来の仕事とはなにか?
なぜ本来の仕事が出来ないのか?
どうすれば本来の仕事が出来るようになるのか?
私を含めたスタークスの全従業員が本来の仕事に能力を注げるよう、まずは業務プロセスの改革に着手する。